京都大学医学部附属動物実験施設報 第2号
附属動物実験施設報第2号の発刊にあたって
京都大学医学部附属動物実験施設
施設長 芹川忠夫
振り返ってみると、動物実験施設のこの2年間は新たな展開への節目であったように感じる。その第1の要因は、長年の懸案であった老朽化した自動飼育装置、高圧蒸気滅菌装置、自動ケージ洗浄装置といった大型の設備の更新が行えたことにある。自家発電装置、沈殿層、給排水設備、給気・排気ファン、エレベータなど更新が待たれるものが控えており、いずれもトラブルが生じると大きな被害を被り、修理にも高額の費用がかかるので、これらについて引き続き新たな更新要求をして行かなければならないが、一息つけた感がある。
第2の要因は、利用者のニーズに応えて、動物実験施設内の模様替えや事業の拡大をいくつか行った点にある。先ず最初は、トランスジェニックマウス、ジーンターゲテッドマウスといった遺伝子操作動物を用いた実験研究が大規模に行われるようになってきたことに対してである。新たに発見された遺伝子の機能をジーンターゲテッドマウスの作製、観察、およびその動物に対する実験処置を通して詳細に検討する場合には、SPF グレードでの実験が求められる。市販されている一般のマウスは、今や SPF であるのが普通となっているが、研究機関等で作製・維持されている動物の場合には、必ずしも SPF とは限らない。そこで、微生物汚染がある場合、またはそれが疑われる場合には、その微生物を除去した動物にクリーン化することが必須となる。このクリーン化を外部機関のみに頼っていては、スムースな運営ができないであろうと考え、動物実験施設においてこれを実施できるようにとシステム作りを進めてきた。平成8年度からは、ネコの飼育室の一部を汚染動物の一時的隔離飼育場所に転用・整備し、さらに SPF の里親用偽妊娠マウスの維持生産室を新たに設けた。そして、体外受精と受精卵移植、あるいは子宮切断術を利用した遺伝子操作動物のクリーン化、及び受精卵によるそれらの凍結保存を小規模ながら事業として行えるように至らしめた。
次に、遺伝子治療の基礎実験を行える場所が求められていたことに対して、P2 組換えウイルス感染動物実験室を新たに設置した。これは、附属動物実験施設内のサル飼育領域の一部を模様替えすることによった。封じ込めレベルが P2 で、使用できる動物種はマウス・ラット等の小齧歯類に限定され、飼育スペースは広くないが、この用途専用の飼育実験室を設けることができたのは、一つの前進であった。
最後は、ヤギ・ヒツジ・ブタ用飼育室と手術室の設置である。この飼育室と手術室は、4室あったイヌの飼育室の1室を模様替えしたものである。これが設置できたのは、イヌの使用数の減少と大きく関わりがあるが、実験目的に適した動物種の選択が強調されるようになってきたからでもある。
以上のように、現有の動物実験施設の改良と機能の充実に努めてきたが、今、利用者から最も要望の多い遺伝子操作動物の飼育スペースの拡大に対しては、残念ながら応じられない状態にある。むしろ、飼育希望者の増加に伴い、これまでの使用者に対して飼育数の制限を求めざるを得ない状況になっている。現有の附属動物実験施設は、このような特殊な動物が存在していなかった時期にできた建物であることから、これらを収容できるスペースがないのは当然のことと言えるかもしれない。医学研究科内の調査成績から試算すると、少なくとも現有の3倍程度のマウス飼育室をもった動物実験棟が必要になる。この利用者の要望に応えるためには、関係各位のご理解とご支援を頂いて具体的な活動を開始して行かなければならない。
稿を終えるにあたり、藤原元典初代施設長(平成6年3月、ご逝去)に続いて、専任教官であった山田淳三名誉教授(元施設長)が平成8年8月にお亡くなりになったことを書き添える。動物実験施設の開設と運営にご尽力された両先生に、関係者を代表して改めて深甚の謝意を捧げ、ご冥福をお祈りする。
(平成8年12月記)
施設報第2号目次へ戻る
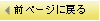  |



